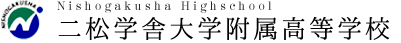男子バレーボール部


男子バレーボール部は、主要大会ベスト32以上に入れるように、日々練習に励んでいます。殆どの選手が高校生からバレーボールを始めました。でも、明るく楽しく前向きに練習に取り組み、みんな上手くなっています。
主な公式戦は、4月の関東大会東京都予選会、5月のインターハイ東京都予選、8月のサマーカップ、9月の第1支部球技大会と春高バレー予選、11月の新人大会、12月のウィンターカップ、3月のスプリングカップなどです。
主な公式戦は、4月の関東大会東京都予選会、5月のインターハイ東京都予選、8月のサマーカップ、9月の第1支部球技大会と春高バレー予選、11月の新人大会、12月のウィンターカップ、3月のスプリングカップなどです。
男子バレーボール部プロフィール
| 人数 | 活動曜日 | 活動場所 |
| 26 | 月・木・土・(日) | 体育室・大学体育館 |
男子バレーボール部からのお知らせ

- 2024年12月7日
- 2024年度 新人大会(一次大会)まとめ
- 11/3〜17の3週間に渡って新人大会(一次大会)が行われました。夏休み中の大会は学校行事(スタディツアー、勉強合宿)や風邪などでフルメンバーが揃わず、6人ギリギリで大会に出場していました。なので今大会はフルメンバーが揃って臨むのが初めての大きな大会となりました。
初日初戦の相手は目黒学院。過去何年かに渡って大会や練習試合で競ってきた相手で、この夏にも練習試合で対戦して競り合いました。案の定この試合も接戦となりました。一セット目はこちらのブロックが相手のエースを自由にさせず、またブロックやアタックのカバーリングも対応できていました。それでもどうにかこうにか25−23の接戦の末セットを取ることができました。二セット目は相手のエースが奮起し、ブロックを避けて打ち込んでくるようになったため、序盤で大きくリードされ、セットを取られました。三セット目は、一セット目同様相手のエースをブロックに捉えることができ、中盤までに17−10と大幅リードを取ることができましたが、終盤に勝利を意識したせいかもたついてしまいますが、どうにか公式戦初勝利することができました。この試合、一セット目の奪取が勝負の分かれ目になったのだと思います。夏から重視して練習、練習試合で調整してきたブロックとブロックカバーが機能するレベルまで上がってきた結果だと思います。二試合目は板橋高校との対戦。一試合目からの連続試合になったので、終盤に足を攣りかける選手がいたのですが、順当に勝利し、2日目へ駒を進めることができました。
2日目はこの大会のベスト32をかけて武蔵野大学附属高校との対決、一セット目はこちらのブロックが機能して相手を自由にさせず25ー14で取り、二セット目は序盤に相手の強気なサーブに苦戦しますが、食らいついて行って、中盤に2年生鶴巻の連続サーブで大幅にリードを作ることができました(21−9)。しかし、終盤に相手が粘りを見せて、ブロックでこちらのスパイクを捉え始めたのですが、どうにか逃げ切り25−15で二セット目も取り勝利。この結果、3日目へ進出を決めるのと同時に、1月19日の新人大会(決勝大会)への出場権、来年春の関東大会予選のシードを手にすることができました。恐らく、二松学舎高校男子バレーボール部にとって史上初のことかと思います。
3日目はベスト32以上のチームが集まっての順位決定戦。東京都の高校バレーの大会で常に上位にくるチームとの対決です。試合会場である中央大学附属高校に到着すると試合会場に入る前から今までとは全く違う異様な雰囲気。どのチームも部員数、応援の人数が多く、中には太鼓やメガホン、横断幕を何枚も持ち込んで、試合開始前から選手も応援も気持ちが高まっていました。少人数の二松学舎は完全に雰囲気に飲み込まれ、ただでさえ少人数で小さくまとまっているのに、より一層小さくなってまとまってしまっているようでした。
3日目の対戦相手は春高常連の東洋高校。日本代表選手を何人も輩出している強豪校です。第一支部球技大会で毎年試合を見たり対戦したりするのですが、そこに出ているチームのレベルとは全く別次元のレギュラーチームでした。そういうチームが相手であっても、ただ闇雲に試合をやっても何も手出し出来ずに終わってしまいます。目標は、ローテーションを一セットで2回まわす、メチャクチャ強い相手に1本でもいいから通用するプレーを出すこととし、試合に臨みました。1、2セットとも10点程度しか取ることしかできませんでしたが、ローテーションを重ねるにつれて東洋の展開に対応していける場面が増えてきて、個々の選手に良いプレーが出てきました。
東洋との対戦を振り返ってみて、次の大会(12月15日、22日の私学大会、1月19日の決勝大会)に向けて修正、調整すべき課題が見つかりました。東洋が見せつけてくれた多彩なコンビに対してブロックマークが遅い、甘いのが試合動画から露呈しました。この判断が遅いと後ろのレシーバーがコースに入りづらくなり、相手のアタックを正面に捉えることができなくなってしまいます。限られた時間ではありますが、少しでもレベルアップできるように練習、練習試合に取り組んでいきたいと思います。
1月19日の決勝大会は来春以降の大会を占う試合になります。決勝大会の上位に入ったチームが来春の関東大会に出場する可能性が高いです。決勝大会でまず1勝できるように、また、今後の大会で上位にとどまれるように練習・練習試合を組んでいこうと思います。
少人数の選手たちだけでは心もとないので、決勝大会では、是非、試合会場に駆けつけていただき、他校の負けないくらいの応援をお願いします。

- 2023年3月22日
- スプリングカップ(3月21日、世田谷総合高校)
- 新年度の大会に向けて練習、練習試合が本格化してきている中、スプリングカップが行われました。3学期の練習、練習試合の中でテーマに掲げていることが「歯車をしっかり噛み合わせる」ということです。バレーボールの「自陣で3回触る」という特性上、認知→判断→伝達→移動→プレー(ボールタッチ)の流れがチーム全体で同調していなければ、ラリーに綻びが生まれミスを誘発し、失点に繋がってしまいます。チームのメンバーが高校生になってからバレーボールを始めた者ばかりで、また、体育館が狭くフルコートを貼れず天井が低いということもあり、ラリー練習を行なって同調性を鍛えていくことがなかなか難しいのが現状です。そんな状態でも最近の練習試合を通して、ようやく同調する意識が芽生えてきました。
今日のスプリングカップでは、前日の練習でレフトのスタメンの選手(新2年生)が怪我をしたため、予選リーグでは急遽スターティングラインナップを変更して臨みました。その影響なのか、ゲームの所々で歯車がうまく噛み合わず、レシーバー間にボールが落ちたり、お見合いをしたりとミスを繰り返す場面が目立っていました。そんな中でもチームの士気を高めるような気持ちの入ったプレー(フライングレシーブや連続ブロックなど)も所々出てきていて歯車が回り始めるのですが、噛み合い切らずに相手に返球できず失点というもったいないシーンもありました。その結果、予選リーグは、対戸山高校(0ー2)、対世田谷総合高校(1−1)となり、得失点差によりリーグ2位で順位決定戦に臨むことになりました。
順位決定戦では、一セットマッチで府中西高校との対戦になりました。府中西は予選リーグではどのチームとも接戦を戦い、粘り強く勝ってきたチームで、アタッカーが4枚揃い鋭く撃ち抜いてくるチームです。予選リーグのような戦い方をしてしまうとあっという間にセットを取られてしまう可能性がありました。しかし、選手達の中でも試合間に気持ちを切り替えて臨もうという話をしていたようで、出だしから認知→判断→伝達→移動→プレー(ボールタッチ)の流れが同調し、乱れた1本目も2タッチ目で修正して攻撃で終わる、最低限相手コートに返すプレーが増えてきました。セット中盤に放されかけたのですが連続ポイントで追いつき、終盤まで1、2点差でシーソーゲーム。しかし、最終的にジャッジミス、サーブミス、サーブレシーブミスで相手を追い込むことができず、23−25で敗戦となりました。終盤に入るまでの戦い方を最終盤でもできていればセットを取れたのかもしれません。やはり、予選リーグでそういう戦い方をしてきた府中西の方が気持ち的に優位に立っていたのかもしれません。春休みの練習、練習試合では、接戦でもしっかり歯車を噛み合わせて気持ちで負けない冷静さを失わない戦い方ができるように鍛錬していきたいと思います。

- 2023年3月22日
- MAKENAI CUP(1月29日、科学技術高校)
- 1月29日、都立科学技術高校にて行われたMAKENAI CUPに出場しました。新人大会を勝ち上がっていれば3日目に当たる日に、新人大会決勝大会の裏大会として実施されています。
この日は、レギュラーのセッターが体調不良で欠席になったため、1年生セッターがフル出場となりました。今までの練習試合では半ローテや1ローテ限定で出ていたので、フル出場は初めてなのですが、そんなことを感じさせないようなトス回しをしていました。
前日の練習後のミィーティングで、「1年生セッターが沢山経験できるように、サーブカットやラリー中のカットなどの1本目のレシーブをしっかり上げるように準備すること」と伝えたのですが、安易なレシーブミスやサーブミスを多発し、本来であればもっとラリーしていたと思うのですが、それが叶わなかったのが残念なところです。
2年生にとっては、引退というものが視野に入ってきているところです。1回1回の練習機会、1本1本のボールが意味合いや重要性が増してきます。準備不足で安易なミスを犯さないよう、練習、アップをしっかりやっていってもらいたいです。

- 2022年11月22日
- 武蔵野の森スポーツプラザ(体育館)にて練習
- 武蔵野の森スポーツプラザ(調布)の体育館で行われた球技大会後に、男子バレーボール部は練習を行いました。プロスポーツや国際大会も開催できる広い体育館での練習で、選手たちも伸び伸びと練習することが出来ました。校長先生にも練習に参加していただき、チーム練習では後衛レフトのレシーバーをやっていただきました。選手たちが打ち込むボールや弾いたボールに素早く反応して繋いだり、床に滑り込みながらレシーブしたりする姿を見て、選手たちからは驚きの声が上がっていました。選手たちにも同様の判断力を身につけていけるよう練習に励んでもらいたいと思います。

- 2022年11月22日
- 新人大会(一次予選)
- 11月20日、城北高校にて、新人大会一次大会が行われました。
新人戦までの練習・練習試合で目標にしていたのは、「判断→声(伝達)とプレー(行動)をチーム一丸となって行う(連携)」、そして「簡単にあきらめない粘りでチームを引っ張る(何度も何度もラリーを続ける)」で、目標達成に向けて日々練習してきました。その成果が試されるのが今大会です。
初戦は佼成学園。序盤から淡々と優勢に進めるものの、こちらのサーブミスで終わることが多く、万が一、相手のサーブが走ったり攻撃が噛み合い始めたりしたら、相手に走らせそうな危うい雰囲気でした。二セット目の途中、キャプテンに対して「次の試合を意識して気持ちと集中力を上げる声がけやプレーをするように」と指示し、判断の声や移動にメリハリをつけてプレーするように意識が変わり、終盤は連続してサーブ権を与えることなくゲームを制することができました。結果は、2ー0(25ー14、25ー14)で初戦突破となりました。
2試合目の対戦相手は日体大荏原。対戦前の見込みでは力は互角。勝てるかどうかは、相手の攻撃を如何に早く正しく判断でき、プレーできるか?厳しいところに返されたとしても諦めずにしつこくボールを追っかけて繋げられるか?です。要は目標として練習してきたことが出せるかどうか?です。1セット目は序盤に相手に走られるものの中盤に鋭いサーブが連続して決まって追いつき逆転。その後は終盤までシーソーゲームとなりますが、レシーブでしつこく繋げてラリーを続けてサーブ権を1回で奪われることがなかったので徐々に点差をつけていき、25ー22で1セット目を取ることができました。二セット目も同じような展開。相手に先に走られるのですが、終盤(17点)までにキャプテンの連続サーブなどで並び、その後は粘り強くフライングレシーブなどでボールを繋いでシーソーゲームになり、主導権を取られないよう耐え続けました。その状況で先に24点を取ったのは二松学舎(相手は22点)。あと1本取ればゲームセットというところで勝利を意識したせいかプレーが小さくなり連続ミスして24−25。ここでサーブ権を取り戻すもののサーブミス。結果、26ー28で二セット目を取られてしまいました。三セット目も中盤までは、1、2セット目と同様の展開。しかし、アタックが相手もブロックに引っかかり始めて決めきれなくなり、粘り強いレシーブも制裁を欠いて主導権を握れなくなり、相手にリードされたままゲームセットとなりました。結果は、1−2(25−22、26−28、17ー25)で敗退となりました。
この試合、苦しい状況を乗り越えて勝利を収めるという大きな経験をできなかったのは大変残念なことです。しかし、ラリーを繰り返すごとに判断が早くなり、的確な声が出るようになり、粘り強さが増していったのは大きな収穫になったと思います。

- 2022年8月27日
- 私学大会(8月16日 vs國學院久我山高校)
- 夏休み前半の練習、練習試合の集大成となるのが、この私学大会です。しかしながら、今回の大会は、スタディーツアーや帰省などでフルメンバーで出場することができず、普段は控えに回っていて、試合にフル出場したことがない選手をスタメンに入れて試合に臨むしかありません。そんな大会以前からの劣勢の状況でも、チームが連動・連携して動くために必要な、判断、声を絶やさず実行できるか、そして、しつこくボールを繋げていけるかどうかが試合を成立させるための鍵になります。
1セット目は、試合経験が浅い選手の周辺が狙われ、チーム全体の動きがチグハグになり、流れが掴めず取られてしまいました。しかし、起こったミスを無駄にすることなく、連動の仕方や判断の声の出し方などを選手同士で確認するコミュニケーションをとりながらゲームを進めていく様子が見られ、チーム一丸となって諦めずに少しでも勝ちに近づこう、成長しようとする姿勢が出てきていました。結果は、17−25で落としました。
2セット目、1セット目のコミュニケーションの成果が出たのか、連動してディフェンスができるようになってきて、粘り強くラリーを続けられるようになってきました。セット中盤から主導権を握り、自分達のペースで試合を進め、25−20でセットを獲りました。
3セット目は15点マッチ。序盤からサイドアウトの繰り返しで、互いにペースを掴めないまま点数だけが進んでいき、セット終盤へ。ここからは連続ミスした方が負けになります。12対12までもつれたものの、最後はボールタッチのミス(ドリブル)を取られて万事急須。(セットスコア13ー15)
フルメンバーではなくてもここまで競るゲームを作れるようになったのは、夏休み中の練習の成果が出てきたのでしょう。また、ゲーム中に修正をかけるコミュニケーションが選手間でできるようになったのも、遠征ウィークで詰めてきた成果が出始めたのでしょう。この大会を終えて見えてきた課題、判断・声出しのタイミング、次のプレーの準備を速くする、個々の選手のボールタッチの精度を上げることを、9月に行われる第一支部球技大会、全日本選手権予選に向けて集中的に練習していきたいと思います。

- 2022年8月27日
- サマーカップ(8月14日)
- 東京都西部地区の高校を中心に集まって行われた地域大会です。勝利数、得失点が順位に影響するので、6日、10日にやってきた練習試合とは異なり、真剣勝負になります。出場チームの中には、大会2日目常連の昭和第一学園、専修大附属がいます。その他の学校に手堅く勝ち、その2校にどれくらい迫れるかが上位に食い込むための鍵になります。
しかし、今回の大会には、スタディーツアーや帰省などでフルメンバーで出場することができませんでした。フルメンバーでなくてもフルメンバーで試合している時と同じように試合ができるかどうかが今回の課題になります。課題を達成するためには、やはり、相手を観察、判断、声(コミュニケーション)を徹底してでき、さらに、チーム全体で連動して動けるかどうか(レギュラーではない選手も動かすことができるような判断と声が出せるかどうか)です。
最近の遠征で意識してきたこの課題について、徐々に意識してプレーすることができるようになってきているのを感じられるようなシーンが見られ、チーム全体で成長しつつある姿を感じられました。ただ、まだまだ手堅く勝利を手繰り寄せられていないので、もっともっと課題に対して堅実にプレーしていけるように練習していききたいと思いました。

- 2022年8月27日
- 茨城遠征(8月10日)
- 当初はサッカー部との合同合宿として企画した茨城遠征ですが、新型コロナウイルス感染予防の観点から宿泊は中止となり、丸1日の茨城遠征(練習試合(vs玉造工業、鉾田第一))に変更されました。
普段対戦しない茨城の高校。東京の学校とは異なるプレースタイルでゲームを組み立ててきました。3タッチ目をスパイクにできなくても、こちらの“間”をついて返球してきて攻撃を組み立てさせないようにしてくる。さらに、こちらが“間”をつく返球をしたとしても、判断よくボールの落下地点に入ってきて、精度の高いレシーブで繋げていく粘り強さをもっている。そのような状況なので、こちらは主導権を掴めず、常に相手のペースでゲームが進められてしまいました。それだけ自信を持って繋げてくれば、攻撃の大胆に力強く打ち込んできて、ミスも恐れない。都内のみの遠征だけでは経験できないことを体験、体感でき、本校選手に身につけてもらいたい力を見せつけられました。今回見せつけられたものを、これからの練習で自分達のものとして体得できるよう練習を積んでいきたいと思います。

- 2022年8月27日
- 夏休みの練習試合(8月6日)
- 1学期期末考査終了後から約3週間、夏休みらしい集中的な練習を行なってきました。8月6日の練習試合を皮切りに、8月16日の私学大会まで遠征ウィークが始まります。
この日の対戦相手の中大杉並と錦城は大会二日目に進出する常連校で、今までの練習で積み上げてきた成果を試すには不足がないチームです。
対戦結果は、各校と1勝1敗でした。やりたい攻撃を何回か繰り出すことはできましたが、やはり簡単には連勝させてくれないチームでした。
このようなチームに確実に勝つために足りないものは、状況判断能力(判断のスピード)、コミュニケーション(判断の声)、移動スピード、粘り強くつなげる力。次の遠征に向けて学校練習の時からその部分を徹底してやっていくと反省していました。
- 2022年7月31日
- 自分たちの目標に向けて直向きに練習
- 昨日、本校野球部は第104回全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)の出場を決定しました。3期連続出場は本校生徒にとっても誇らしいことでしょう。
男子バレーボール部の選手達は、今日も自分たちの目標に向けて練習です。ここに来て、2年生のレシーブとトス、つなぎの精度が上がり始め、攻撃のバリエーションが増えてきています。新型コロナウイルス感染予防に努めながら、練習の時間と頻度を増やしてやってきた成果が出始めているのでしょう。
これからは実践でいかにそのようなプレーを出すかが大事です。そのようなプレーを出すために必要な判断、準備、声出しなどを徹底的に練習し、8月6日、10日に実施予定の練習試合に臨んでいきたいと思います。

- 2022年6月22日
- 日本武道館をバックに、校長先生と対人パス
- 6月18日、この日は2年生が柏集中体育のため1年生のみの練習。大学体育館を使えなかったため、屋上でパス練習やレシーブ練習を行なっていました。そこへ、柏集中体育の引率から戻られ、校舎内で活動する部活の様子を見て回られていた校長先生が屋上に来られ、急遽生徒たちと対人パスをしていただくことになりました。生徒たちは、パスがずっと続いてボールが落ちないので、校長先生のうまさに驚いていました。ちなみに、校長先生は、バレーボールを選手としても指導者としても経験されています。

- 2022年6月22日
- 新体制スタート
- 3年生が引退し、新体制がスタートしました。6月からは先々代キャプテンを学生コーチとして招いて一緒に混ざって練習と指導をしてもらっています。この日は、2年生が柏集中体育だったので、1年生のみの練習。いつも練習している大学体育館が使えないため、屋上で練習しました。ウォーミングアップで4対2のパスサッカーゲームをしました。視野を広げるためのトレーニングです。その後、対人パスやレシーブ練習を行いました。1年生は全員初心者なのですが、日々上手くなってきています。
- 2022年6月22日
- インターハイ予選
- インターハイ予選で都立戸山高校と対戦。1セット目は中盤までは競るものの、サーブミスを犯して主導権を握りきれず11ー25で落としました。2セット目は戸山高校に序盤から一気に走られ、一時ダブルスコアをつけられましたが、中盤から相手のアタックをブロックワンタッチで利用したり、アタックコースを限定させたりすることができ、点差を詰めていくことができましたが、やはりここでもサーブミスでリズムを作れず、17ー25でセットを落とし、初戦敗戦になりました。3年生はこの大会を持って引退になります。選手2人、マネージャー1人で、1、2年生の部員18名を引っ張ってきてくれました。3年生への恩は、自分たちの成長した姿で返してくれることでしょう。